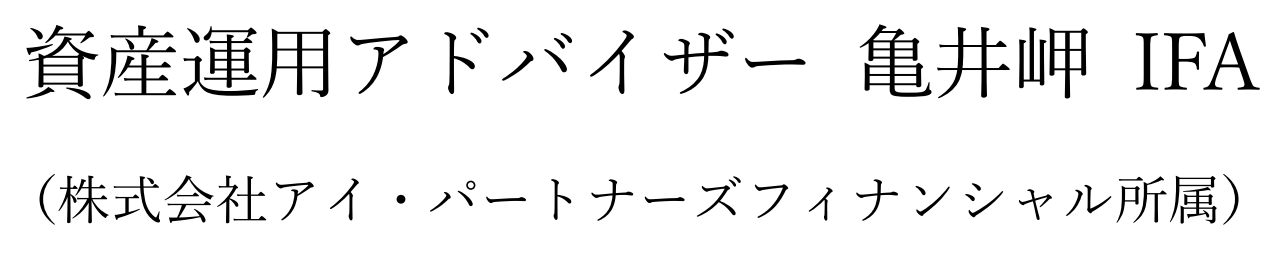【亀井岬IFAコラム】富裕層の資産運用:資産を守るための「心のクセ」入門
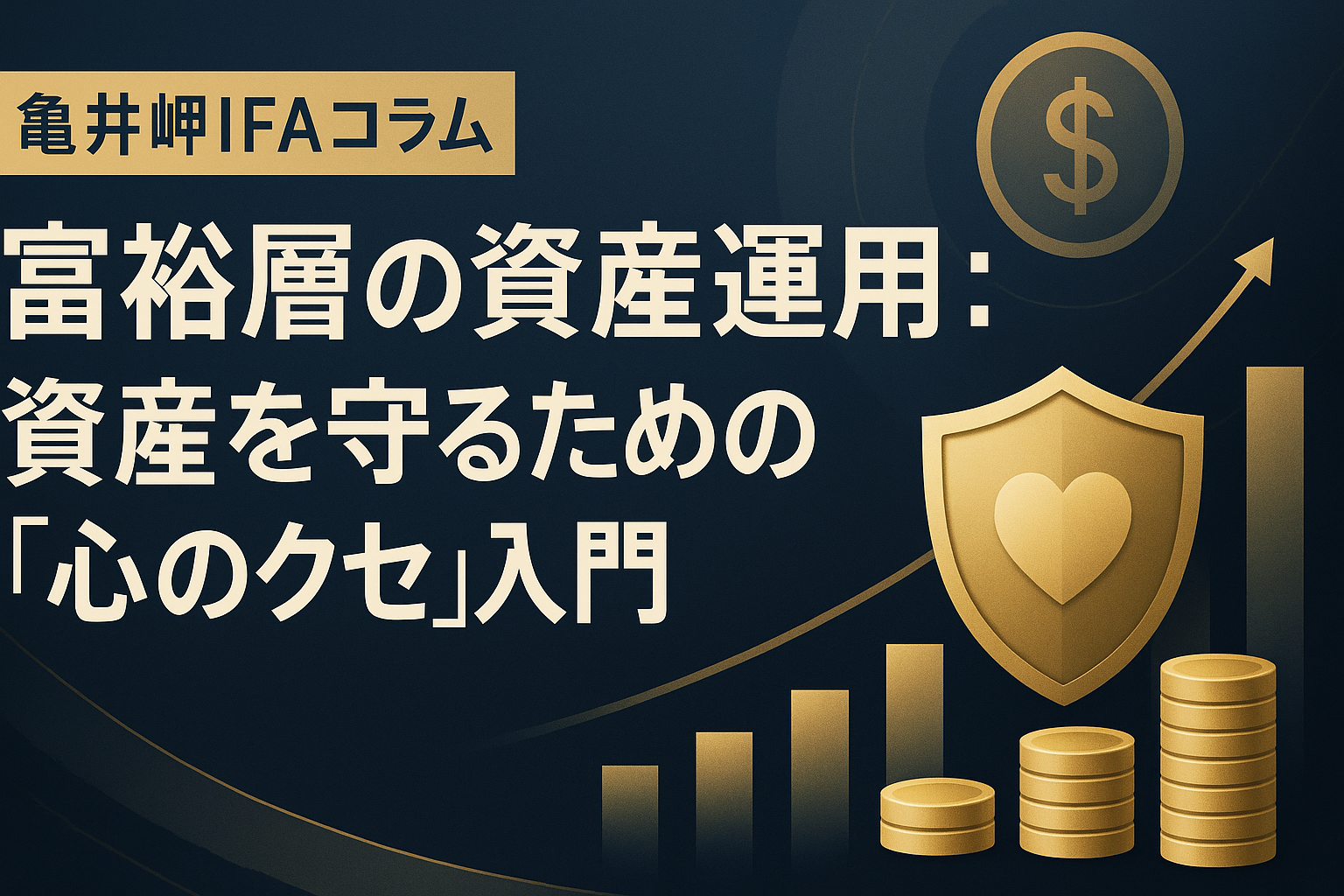
2025年7月2日(水)
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの所属IFA、亀井岬と申します。
金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々からご相談をお受けしております。
専門家や機関投資家が愛用するブルームバーグの専用情報端末を利用し、債券分析やポートフォリオ分析を行っております。現在は数十世帯から数十億円の資産を仲介する証券口座で管理し、資産運用のアドバイスを行っております。
本日は「富裕層の資産運用:資産を守るための「心のクセ」入門」という内容についてお話させていだければと存じます。最後までご覧いただけましたら幸いです。
またポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談に関しましては以下のフォームよりお申込みいただけましたら幸いです。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から承っております)
富裕層の資産運用:資産を守るための「心のクセ」入門
従来の経済学では、人間は常に冷静に計算して行動するものと考えられてきました。しかし、心理学を取り入れた「行動ファイナンス」という新しい考え方によれば、私たちの判断は「思い込み」や「感情のクセ(バイアス)」によって、いつの間にか合理性を失ってしまうことが分かっています 。
この「心のクセ」は、頭の良さや経験に関係なく、誰にでも起こりうることです 。むしろ、自分の判断力に自信がある人ほど、「自分は大丈夫」という自信過剰からリスクを見誤ってしまうことさえあります 。資産が大きい富裕層にとって、この問題はより深刻です。ほんの少しの判断ミスが、何百万、何千万円という大きな損失に直結しかねないからです。
この記事では、富裕層の投資家が特に陥りやすい3つの「心のクセ」——「損失への過剰な恐怖」「持っているものへの愛着」「過去へのこだわり」——に注目します。そして、そのクセの正体を解き明かし、どうすれば乗り越えられるのか、具体的なヒントをお伝えします。ご自身の「心のクセ」と向き合い、より冷静で賢い投資家になるための、第一歩となれば幸いです。
・含み損に狼狽えていないか?
・保有効果に惑わされていないか?
・サンクコストに固執していないか?
【関連記事】

含み損に狼狽えていないか?
持ち株の評価額がマイナスになっているのを見ると、どんなに経験豊富な投資家でも、不安や焦りを感じるのは当たり前のことです。それは決して気が弱いからではありません。「損をしたくない」という気持ちは、私たちが危険から身を守るために備わった、ごく自然な本能だからです。
しかし、この本能が、実体のない金融市場という数字だけの世界では、資産を増やす上での大きな障害になることがあります。市場が下がったときのあなたの判断は、冷静な分析に基づいたものでしょうか? それとも、損をすることへの本能的な怖さに動かされていませんか? この問いに正直に向き合うことが、賢い投資家への第一歩です。
・損失回避は同額の利益より約2倍強く痛みを感じる
・メディアのニュースに不安を煽られていないか?
・利益の出た銘柄を早売りし、損失となっている銘柄を塩漬けにする傾向はないか?
- 1.損失回避は同額の利益より約2倍強く痛みを感じる
-
行動ファイナンスの重要な考え方に「プロスペクト理論」があります。その中でも特に知られているのが、「人は損をすることに非常に敏感だ」という性質です 。研究によると、私たちは利益を得た喜びよりも、同じ金額の損失を被ったときの苦痛を、約2倍から2.5倍も強く感じると言われています 。
つまり、1,000万円儲かったときの嬉しさよりも、1,000万円損したときの精神的なショックの方が、はるかに大きいということです 。この感情のアンバランスが、投資判断を狂わせる原因になります。資産の大きい富裕層にとって、この影響は無視できません。金額が大きい分、損失がもたらす心のプレッシャーも相当なものになります。
- 2.メディアのニュースに不安を煽られていないか?
-
「〇〇ショック、再来か?」「株価大暴落!」といったメディアの見出しに、心臓がドキッとした経験はありませんか? 1でお話したように、人は利益の喜びより損失の痛みを強く感じる(損失回避性)ため、こうしたネガティブなニュースに本能的に強く反応してしまいます。
メディア、特にオンラインメディアの目的は、人々の注目を集めてクリックや視聴を促すことです。「市場は安定的に推移しています」という事実よりも、「未曾有の危機が迫る」といった刺激的な見出しのほうが、はるかに多くの人の目にとまります。その結果、短期的な市場の上下動や一部のネガティブな事象が、まるで市場全体の未来を左右するかのように、過剰に大きく報じられる傾向があるのです。
このような情報に日常的に触れていると、冷静な判断が難しくなります。本来は長期的な視点で立てたはずの投資戦略を忘れ、恐怖心から「今すぐ売らなければ」と、衝動的な売却(狼狽売り)に走ってしまうのです。これは、まさに「損失の痛み」を避けたいという本能的な感情に、メディアの情報が拍車をかけている状態と言えます。
大切なのは、メディアのニュースと意識的に「距離を置く」ことです。短期的なノイズに惑わされず、ご自身の投資方針や長期的なゴールに意識を集中させることが、資産を守り育てる上で極めて重要になります。
- 3.利益の出た銘柄を早売りし、損失となっている銘柄を塩漬けにする傾向はないか?
-
メディアのような外部からの情報だけでなく、私たちの心の中に根付く「損失への恐れ」は、日々の売買判断そのものにも直接的な影響を与えます。その最も代表的なパターンが、利益が出ている銘柄と損失を抱えている銘柄とで、全く逆の行動をとってしまうことです。
まず、少しでも利益が出ると、「この利益がもし無くなってしまったら」という損失への恐怖が先に立ち、まだ大きく成長する可能性のある優良な資産を、焦って早々に売却してしまいます(利益確定の早期化)。
その一方で、損失を抱えた銘柄は「塩漬け」にしてしまいがちです。こちらは「損失を確定させたくない」という気持ちが強く働き、売却して損失を現実のものとする苦痛を避けるため、「いつか価格が戻るはずだ」と期待して保有を続けてしまうのです(損失確定の先送り)。
このように、「利益はすぐに確定(利小)し、損失は放置して拡大させる(損大)」という行動は、プロスペクト理論が示す典型的な心のワナです。長期的に見ると、資産を大きく減らしてしまう原因になりかねないため、常に意識しておく必要があります。
【関連記事】

保有効果に惑わされていないか?
人は、あるモノを「自分のものだ」と思っただけで、その価値を客観的な評価以上に高く見積もってしまう傾向があります。これを行動ファイナンスでは「保有効果」と呼びます 。自分の愛車を売るときに、相場より高い値段を付けてしまうのが良い例です。
このささやかで強力な「心のクセ」は、金融資産にも影響を与え、私たちが既に持っている資産に対して、見えない「感情的なひいき目」を加え、冷静な判断を曇らせます。今一度、自問してみてください。その資産を保有している理由は、将来有望だからですか? それとも、単に「前から持っているから」ですか?
・親から受け継いだ資産を「特別なもの」だと思い込んでいませんか?
・「社会のため」という気持ちが、冷静な判断を邪魔していませんか?
- 1.親から受け継いだ資産を「特別なもの」だと思い込んでいませんか?
-
「保有効果」は、相続で得た資産に対して特に強く働くことがあります。相続した株や不動産は、単なる資産ではありません。そこには、親から子へという想いや家族の歴史といった、感情的な価値が乗っかっています。この感情的なつながりが、「このままでいいや」という「現状維持バイアス」と結びつくと、変化に対する強い抵抗感が生まれます 。
多くの人は、相続した資産をポートフォリオの中でも「特別なもの」として扱いがちです。他の資産であれば行うはずの、厳しいパフォーマンスチェックや合理的な分析の対象から、無意識のうちに外してしまうのです。判断の基準は「この資産を売るべきか?」ではなく、「父が遺してくれたこの株を、売ることなんてできない」という感情的な答えにすり替わってしまいます。
これは、多額の資産を相続する可能性のある富裕層にとって、非常に大きな問題です。相続資産は、特定の会社の株や一族代々の土地など、偏った形で受け継がれることが少なくありません 。これらを感傷的な理由だけで持ち続けることは、資産のバランスを大きく崩し、あなた自身の人生設計やリスクの考え方と合わなくなる危険があります。さらに、相続の手続きが面倒なことも、「何もしない」という選択を後押ししてしまいます 。
ここで大切なのは、相続資産に対する見方を変えることです。私たちはつい、資産が誰から来たのかという「過去」の視点で見てしまいます。しかし、合理的なアプローチは、まずその資産を心の中で「現金」に置き換えてみることです。そして、こう自問するのです。
「もし今日、この評価額と同じ現金を相続したとしたら、私はそのお金で、わざわざこの資産を買い直すだろうか?」
この問いかけは、資産を「守るべき遺産」から「活用すべき資本」へと見方を変えてくれます。遺してくれた人の想いを大切にすることは、必ずしも資産の「形」を維持することだけではありません。その「価値」を賢く管理し、次の世代へとつないでいくことでも実現できるのです。
- 2.「社会のため」という気持ちが、冷静な判断を邪魔していませんか?
-
環境や社会に配慮した「ESG投資」は、素晴らしい考え方です。しかし、投資先が持つ社会的な価値への強い共感が、一種の「保有効果」となり、客観的な投資判断を歪めてしまうことがあります。
投資家は、ある企業が掲げる「社会貢献」という使命に共感するあまり、その株を持っていること自体に満足してしまうことがあります。その結果、その判断を正当化するような良い情報ばかりを探し、財務パフォーマンスの悪化といった都合の悪い情報から目をそらす「確証バイアス」に陥りやすくなります。
このリスクは、ESG投資が抱えるいくつかの課題によってさらに大きくなります。例えば、ESGの評価基準が会社によってバラバラであること 、実際は環境に配慮していないのにそう見せかける「グリーンウォッシュ」の問題があること 、そしてESG投資は成果が出るまでに時間がかかること など、注意すべき点が多くあります。
自分の資産で社会に貢献したいという願いは、とても尊いものです。しかし、その際に「社会貢献活動」と「投資」をはっきりと区別することが重要です。ESG投資もあくまで「投資」である以上、リターンを生み出すことが期待されます。パフォーマンスが悪いのに「気分が良いから」という理由だけで持ち続けるのは、資本の無駄遣いかもしれません。そのお金は、もっと良い投資先や、もっと直接的な社会貢献活動に使うこともできるはずです。
【関連記事】

サンクコストに固執していないか?
「ここまでお金と時間をかけたんだ。今さらやめられない」。この考え方は「サンクコストの罠」または「『もったいない』の罠」として知られ、多くの失敗の原因となってきました 。サンクコストとは、すでに支払ってしまい、もう二度と取り戻すことのできない過去のコスト(お金、時間、労力)のことです。
私たちは、この取り戻せないはずのコストを惜しむあまり、将来の判断を誤ってしまうという、おかしなクセがあるのです 。投資の世界では、これが「損な投資にさらにお金をつぎ込む」という形で現れることがあります。ここで自問すべきは、今の判断が、その資産の「将来性」に基づいているのか、それとも変えられない「過去」に縛られているのか、という点です。
・目に見える基準となる価格に惑わされていないか?
・解約ペナルティを理由にパフォーマンス不振の商品を保有し続けていないか?
・すでに支払った労力と時間に惑わされていないか?
- 1.目に見える基準となる価格に惑わされていないか?
-
人は、最初に示された情報(特に数字)に強く影響され、その後の判断がそれに引っ張られてしまう傾向があります。これを「アンカリング効果」といいます 。投資の世界で、最も強力な「錨(アンカー)」となり得るのが、資産の「購入価格」です。
例えば、ある株を1株10,000円で買ったとします。その後、株価が7,000円に下がりました。この株を持ち続けるか売るかの合理的な判断は、その会社の将来性や他の投資先との比較で行うべきです。しかし、多くの場合、私たちの頭は「10,000円」という数字に縛られてしまいます。
目標が「良い投資をすること」から「買った値段まで戻すこと」にすり替わってしまうのです。会社の業績が悪化していても、この「購入価格」というアンカーに戻ることを期待して、不合理な保有を続けてしまいます 。
この心のクセは、意思決定の基準を「未来」から「過去」へと歪めてしまう点に問題があります。合理的な投資判断は、「この資産は将来いくらの価値になるか?」という未来志向の問いから始まります。
しかし、アンカリング効果は、このプロセスを乗っ取り、「今の価格は、自分が払った価格と比べてどうか?」という過去志向の問いに変えてしまいます。
市場は、あなたがいくらで買ったかなんて全く気にしません。この罠を乗り越えるには、意識的に「錨を引き上げる」努力が必要です。すべての資産を「まっさらな状態」で評価し、「もし今日、初めてこの資産を買うとしたら?」という視点で判断する習慣が求められます。
- 2.解約ペナルティを理由にパフォーマンス不振の商品を保有し続けていないか?
-
「もったいない」の罠の典型例が、金融商品の解約ペナルティです。これは、将来どんな判断をしても、一度払えば戻ってこない、典型的なサンクコストです 。しかし、私たちはしばしば、このコストを将来の判断に誤って含めてしまいます。 非合理的な考え方はこうです。「今解約したら、高いペナルティを払わなければならない。それは損を大きくするだけだ」。
しかし、合理的な考え方は全く違います。比べるべきは、成績の悪い商品の「将来の期待リターン」と、もっと良い投資先の「将来の期待リターン」です。ペナルティを払うのが嫌で質の悪い投資を続けるのは、お金を払ったからという理由で、つまらない映画を最後まで見続けるのと同じです。それはただ、損な時間を長引かせるだけなのです 。
富裕層の方は、複雑な仕組みの商品や、長期の解約制限、高額なペナルティが設定された商品を保有していることも少なくありません。ペナルティの金額が大きいと、それが心理的な壁となり、投資の前提が崩れても、適切とは言えない投資を続けてしまう原因になり得ます。
今回の罠の根底には、「損失の二重計上」という心の錯覚があります。まず、元本が値下がりして含み損が出ます(損失①)。次に、解約するにはペナルティを払う必要があります(損失②)。私たちは、この二つを一つの巨大な痛みとして捉えがちです。
しかし、常に解約に一定のペナルティを支払う必要があるのであれば、それは途中解約するのであれば必ず発生するコストと捉えられるのではないでしょうか。つまり本当に考えるべきは、将来のパフォーマンスです。「このまま持ち続けて失う将来の利益(機会費用)」と「今払う一回きりのペナルティ」、どちらが大きいのか?と問い直すことで、合理的な答えが見えてくるはずです。
- 3.すでに支払った労力と時間に惑わされていないか?
-
サンクコストは、投下した資金(お金)だけではありません。ある投資対象を懸命に調べ、選び抜き、日々の動向を追い続けるために費やした膨大な時間、労力、そして情熱もまた、判断を縛る強力なサンクコストとなります。
多大な努力を注いだ投資が不振に陥った時、それを見限ることは、自らの努力が「無駄だった」と認めることに他なりません。これは自身の失敗を認める行為であり、私たちは本能的に強い抵抗を感じます。「過去の自分の判断は正しかったはずだ」という思いが、損切りの適切なタイミングを逃させ、かえって損失を拡大させてしまうのです。
この心理的な罠は、たとえば特定の分野を深く研究してきた専門家や、難関試験を突破した経験のある人などが陥りやすい傾向があります。こういった方は「徹底的に調べ、分析した」という努力が正しい結果に結びつく経験を重ねているため、「これだけ時間をかけたのだから、この投資は成功するはずだ」と強く信じ込んでしまうのです。しかし、投資の世界では、かけた労力と結果は必ずしも比例しません。
この「労力というサンクコスト」が引き起こす最も根深い問題は、投資を合理的な「判断」から、個人的な「プライド」の問題へとすり替えてしまう点です。含み損のある銘柄を売却することが、金銭的な決断ではなく、自身のプライドを傷つける行為のように感じられてしまうのです。
この罠を克服する鍵は、意思決定の仕組みを「ルール化」することです。ルールを設定することで、判断のプロセスから自分の感情やプライドを切り離すことができます。その結果、損切りは個人的な「失敗」ではなく、あらかじめ定めた計画を遂行する冷静な「作業」へと変わるのです
【関連記事】

私にご相談いただくメリット
今回の記事は皆さまのお悩みやご関心に沿うものとなっていたでしょうか?私は冒頭でお示ししましたように、金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々から投資に関するご相談をお受けしております。
以下は手前味噌ではございますが、ご相談の際に特にご好評をいただき「亀井に相談して良かった。」とおっしゃっていただいているポイントでございます。
- 専用情報端末を使ったリスク分析・債券分析
- 大学での講師経験に基づいたライフプラン作成
- 蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験
- 1.専用情報端末を使ったリスク分析・債券分析
-
私はプロの機関投資家も愛用するブルームバーグという専用情報端末を用いて、様々な分析を行っています。
ブルームバーグは相応の費用がかかることもあり、IFAとして活動しているアドバイザーは日本に数千人存在しますが、このシステムを導入しているようなアドバイザーは1%もいないのではないでしょうか。
少なくとも私は過去1人しかお話を伺ったことはございません。ブルームバーグを用いることで、①ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ② リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ③ ご相談者ごとの理想的な資産配分等の分析が行えます。
実際に分析を行わせていただいたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」など、さまざまなご感想をいただいております。
また債券は一般にはその情報が公開されていることが少ないため、上述のブルームバーグのような専用情報端末を用いた分析が欠かせません。債券の値動き分析、ご要望に合わせた債券の発掘など様々な側面でお役に立つお話をさせていただいております。
- 2.大学での講師経験に基づいたライフプラン作成
-
私は2023年4月より2年間にわたって、年に26コマ、私立大学にて『投資教育・ライフプランニング』の講義を行ってまいりました。その経験で培ったライフプランニングの考え方に基づき、ご相談者様それぞれのお立場に合わせたライフプランニング作成を行っています。
- 3.蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験
-
野村證券では、シンガポール社費留学時代に数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究しました。また帰国後、超富裕層に対して資産運用アドバイスに従事したのち、三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、債券知識の研鑽に努め、現在まで16年に亘って富裕層の方々に対する資産運用アドバイスを行っております。
どのようなお悩みでも構いません。よろしければ亀井岬までご相談くださいませ。この度は長文をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
ご相談
ポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談は以下のフォームよりお申込みくださいませ。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から承っております)

プロフィールへ
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲) 第314号
個別相談ではご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
金融商品を対象とした投資には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として価格が変動するリスクにより、損失を被ることがあります。また、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資では、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
本記事は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は金融商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するものではありません。
本記事はある特定の投資目的や金融ポジション、あるいは特定のニーズにこたえたものではありません。将来的には予想通りの結果とならない可能性があります。本資料で取り上げられている投資対象や投資戦略の適正については投資アドバイスを受けることをお勧めします。投資利益あるいは投資対象の価格・価値は変動する可能性があり、投資収益が投資額を下回る場合もあります。
投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。
・所属金融商品取引業者等
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号、商品先物取引業者
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第67号
(加入協会)
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第140号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会
野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第373号
〈加入協会〉
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。